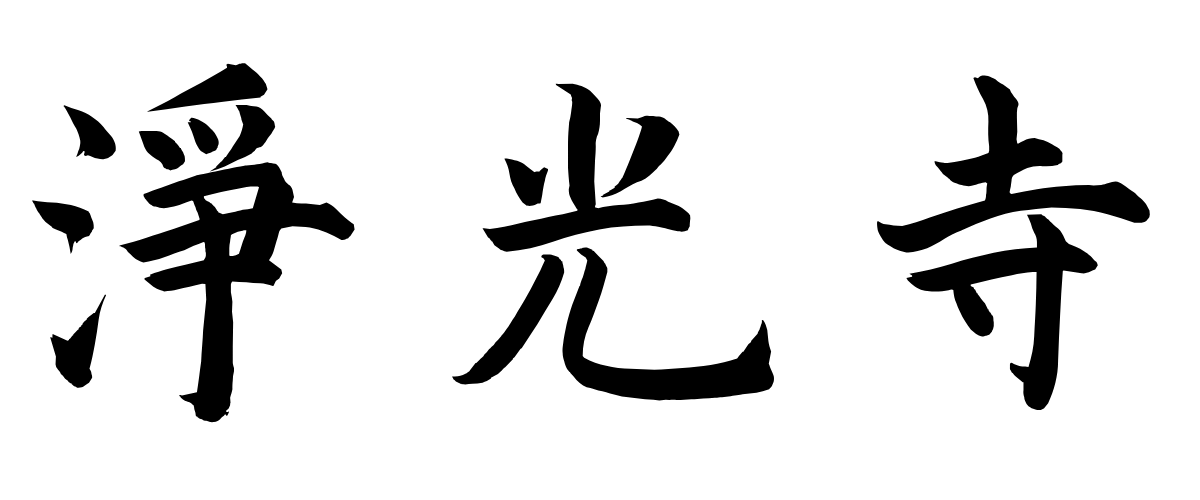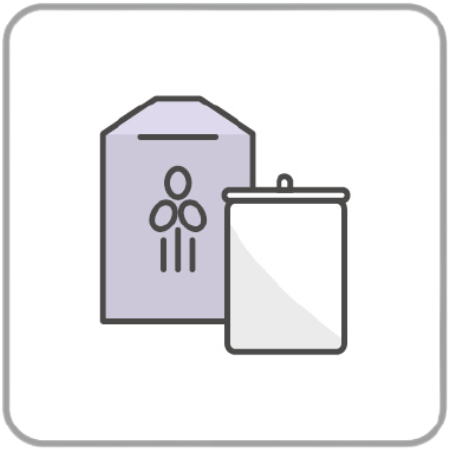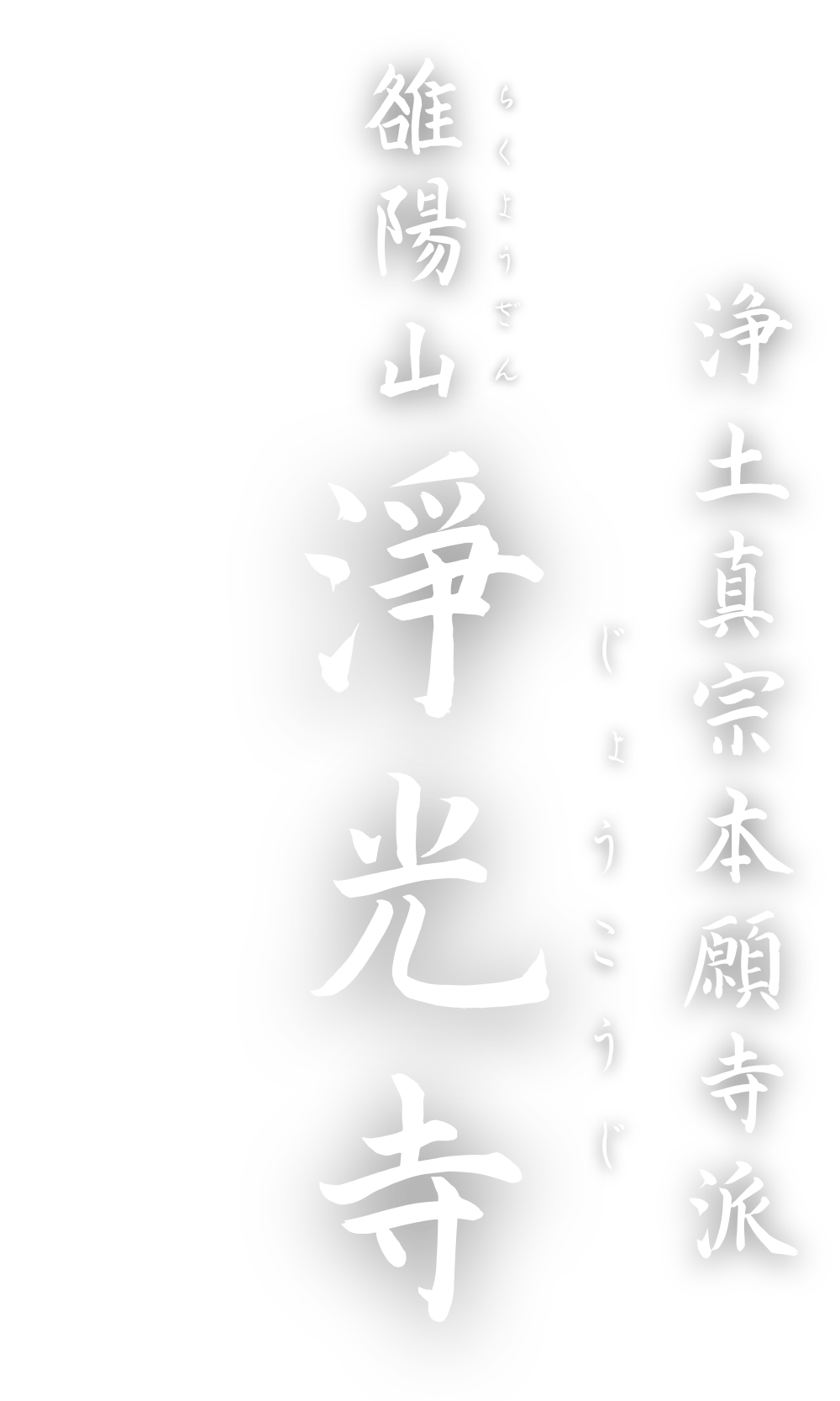
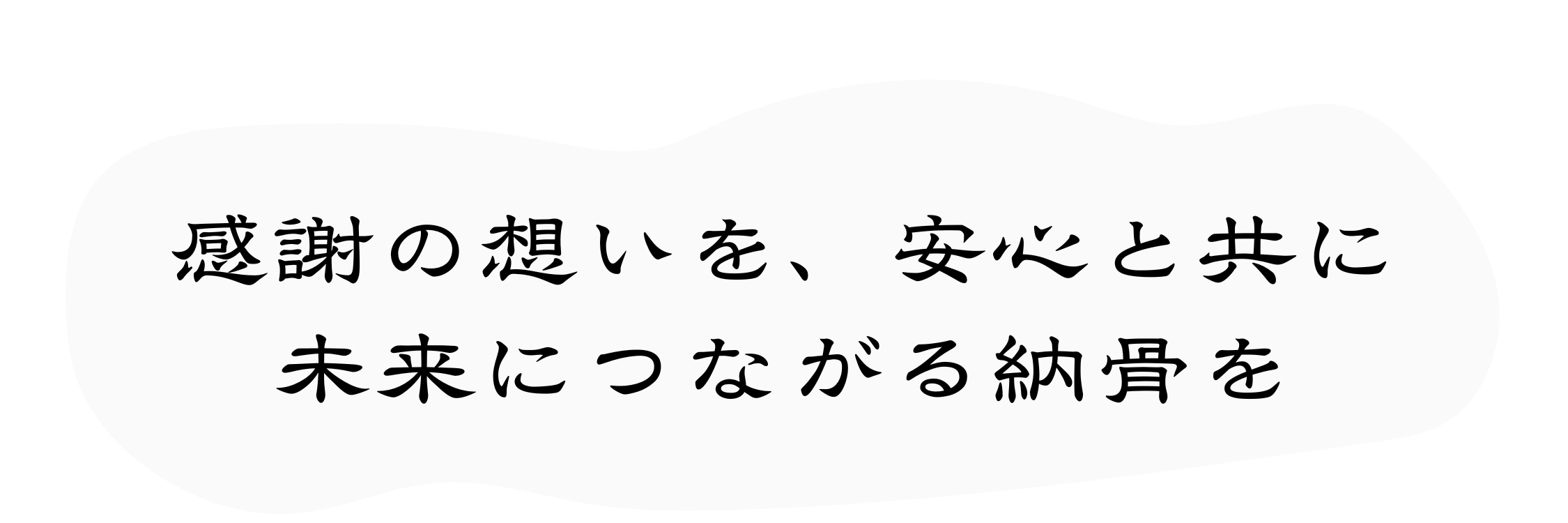

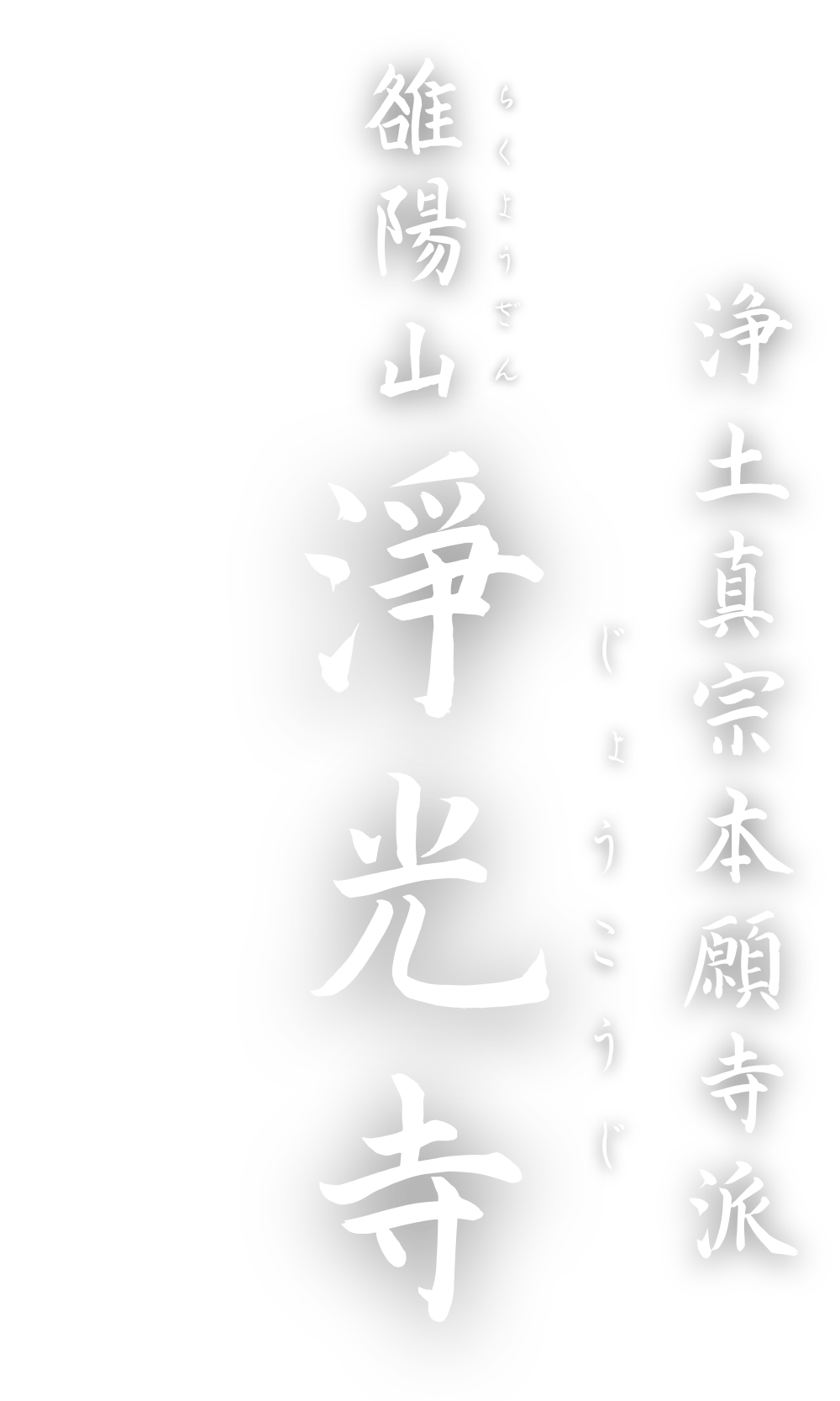
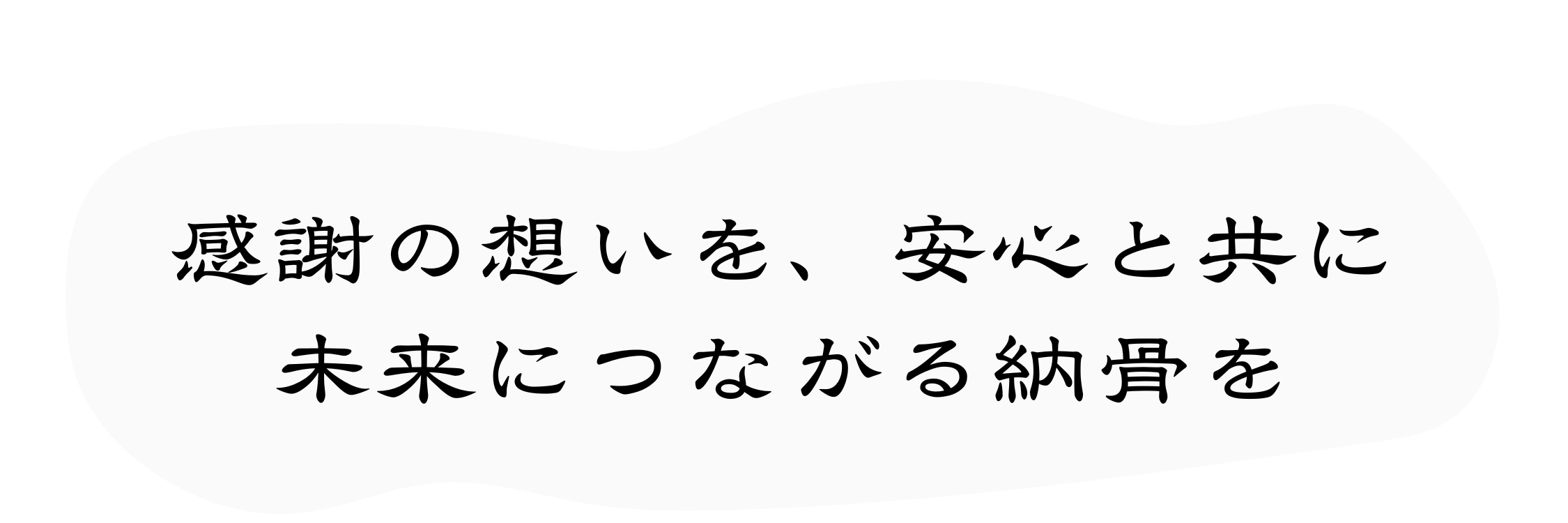
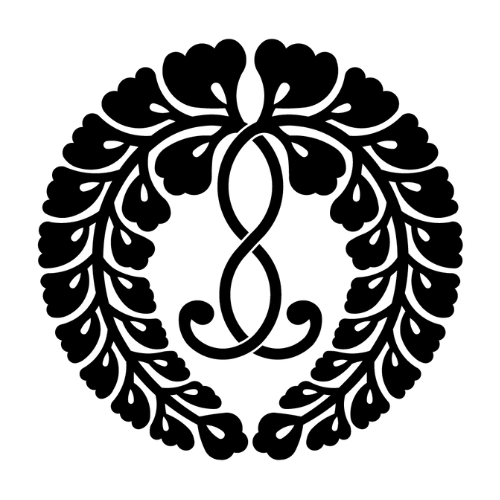
こんなギモンやご要望は
ございませんか?
仏事FAQ
\ 全て、浄光寺がお応えします。/
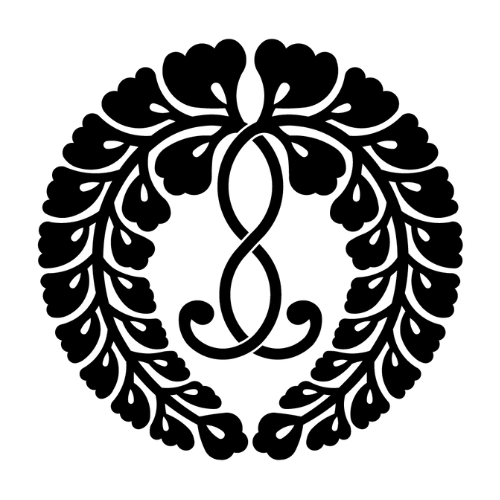
納骨
こんな方におすすめ

跡継ぎがいない方

生前に決めたい方

お墓の管理が難しい方

身寄りのない方

納骨について
近年、承継する者もいないとの理由から、墓地の建立をされない方。また、自己所有の墓地の維持(承継)が困難になり、いわゆる“墓じまい”をお考えの方も多くなってきました。
浄土真宗本願寺派(西本願寺)では、宗祖親鸞の廟所である大谷本廟(通称:西大谷)の明著堂に納骨を行うことが一般的であります。
浄光寺の納骨墓
當山淨光寺も、西大谷墓地内(正式には鳥辺山延念寺旧跡墓地)に納骨墓を所有しております。
正式名称は 淨光寺門徒別墓といい、春秋の彼岸期間の最後の土日祝の午後2時より、當山門徒(檀家)のご遺骨が埋葬してありますこの墓地において、納骨者法要を行っています。
- この墓地には、當山歴代住職の遺骨も分骨しております。
- 納骨は、年中いつでも可能ではありません。
- 秋の法要の時の、年に一度だけ可能です。
- 合祀ですので、一度納骨されたご遺骨はお返しが出来ません。
當山門徒(檀家)であれば、どなたでも納骨できます。
納骨の費用や永代経については、住職にお尋ねください。

永代供養について
世の中では 永代供養という言葉が使われていますが、少し意味合いが異なります。
浄土真宗では 永代供養という読経や法要は行っておりません。
浄土真宗で言う永代経(永代経法要)とは、亡くなられた方に対する供養を行うのではなく、亡くなられた方を追悼(追善供養ではありません)しつつ、私たち生きている者(命を生かされている者)が、亡くなられた方の代わりに仏さまに感謝するための法要です。
一般の法要(1周忌や3回忌等)は、亡くなられた方に代わってではなく、自分たちの気持ちとしてその故人に感謝のおつとめをしますが、永代経はあくまでも故人の代わりに行うものです。
- 自分たちが高齢になってきた。
- 仏事を継承する子がいない。
- 子どもが女性のみで嫁いでいる立場の娘にお願いしづらい。
- 子どもや孫に負担(お金や時間)を掛けたくない。
- 子である自分が嫁いでしまったため、その後の仏事をさらにその子にまでつめとさせられない
現代の皆さまは、さまざまな状況下に置かれておられます方が増えてきました。今まで、故人の代わりに行ってきた法要を、どこかのタイミングで菩提寺のお寺に今後一切任せようとお考えの方が近年本当に多くなってまいりました。
回忌法要だけではなく、特に墓地がそうです。
墓じまいという言葉を良く耳にする事が多くなりました。
お寺も、檀家さまの家庭事情はある程度掌握しておりますから、お寺の方から「今後お墓はどうされますか?」「今後の仏事はどうされますか?」とお尋ねする事も増えてまいりました。
ただ。「永代経のお布施をお包みしたから、これで今後はもう何の読経もしなくて良い」とお考えの方が多いのですが違います。永代経法要を行った檀家さまには、以降お寺からの回忌法要のご案内は致しませんが、お身体がお元気な間は、ご案内せずともお寺にご連絡いただければ、もちろん戸別の法要は行いますし、法要を行わなくとも、ご命日にはどこかでいつも以上の気持ちで手を合わせて頂きたく思います。
毎年5月15日頃には、永代経の懇志(お布施)を頂いた檀家さまのお名前をお読み上げしての合同のおつとめ≪淨光寺総永代経追悼法要≫を行っています。これは、その対象の皆さまへのご案内は致しておりませんで、住職だけで本堂でおつとめを行っています
京都市中京区 浄光寺
お悩み、費用面、なんでもご相談ください
京都市中京区 浄光寺
\
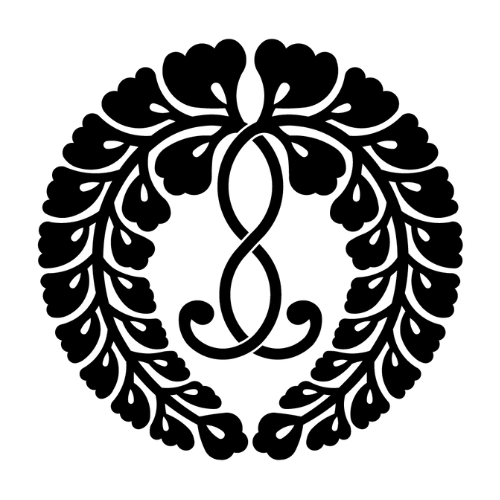
葬儀
こんな方におすすめ!

葬儀の費用を少しでも抑えたい方

家族葬でお願いしたい方

歴史のある寺院にお願いしたい方

まずは葬儀だけお願いしたい方

四十九日以降もしっかり法事をしたい方

直葬を後悔されている方

葬儀について
ご親族さまがご逝去されてからの行動は、本当に時間に追われて大変なものです。特に、高齢のご親族さまがご存命の時から所謂【終活】を行う事にためらいを持たれる方もおいでだとはお思いますが、出来るだけ事前からお寺さまとの相談をされることをお勧めいたします。葬儀社やお寺との金銭にまつわるトラブルも耳にします。ご逝去後にすべてを行うのは無理があっても、なくなく進めてしまう方が多い事も耳にします。そのような事にならないためにも、お寺とのお付き合いは少しでも早くから始められることをお勧めいたします。宗教(仏事)とは、私たち生かされている(生きている)者のために存在しているのですから。
お布施(料金)について
様々なご事情などあるかと思いますので、ご相談に応じて細かく設定しております。
ご家族とお会いした段階で、ご相談させていただきます。


ご相談・ご質問
ご葬儀に関して、分からないことやご不安なことは多々あると思います。葬儀の段取りや費用面、今後のお付き合いなどご家族の事情を考慮しながらご相談をお受けいたします。
京都市中京区 浄光寺
\
京都市中京区 浄光寺
お悩み、費用面、なんでもご相談ください
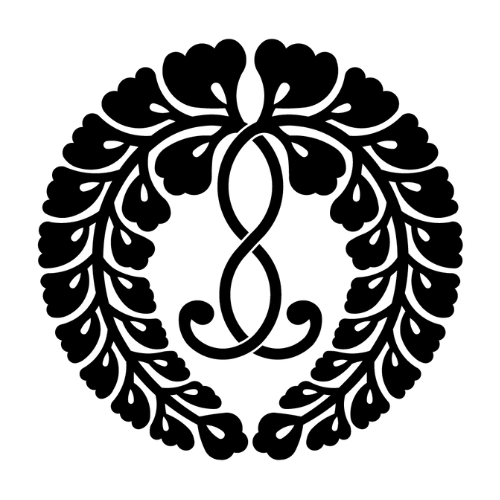
法事法要
法事・各種法要のご依頼やご相談も承っております。
葬儀前であっても、仏事についてのご相談にも対応しております。
ご依頼前に
法事を勤めるのにお困りの方や、長らく法事をお勤めできていない方など、法事やその他、各種法要の件でお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。
会場について
法事・法要には、ご自宅やホールなどへ出向いたしますが、本堂をご利用いただくこともできますので、ご要望の方はお申し付けください。
法事について
葬儀を他のお寺でされた方でも、各種法要のご依頼を承ります。
その他にも事情やご要望がございましたら、まずは当ページよりお問い合わせください。
京都市中京区 浄光寺
\
京都市中京区 浄光寺
お悩み、費用面、なんでもご相談ください
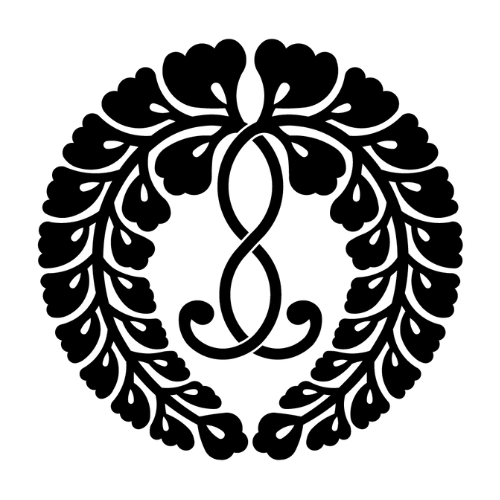
縁起
織田信長との10年に及ぶ石山合戦(当時の本願寺の本山:石山本願寺)において、1580年(天正8年)朝廷からの和議を受け入れた本願寺教団は、大坂:石山本願寺を退去し、紀州鷺森~貝塚と寺基移転を行ったのち、京都の市街地区画整理を行なった豊臣秀吉からの土地寄進により、大坂天満から京都堀川六条へ寺基(本山)移転:1591年(天正19年)を行った。
当時の本願寺第11代宗主は、第8代宗主蓮如のひ孫である第11代宗主の顕如。
その天満から京都への寺基移転の随行の1人だった釋宗安が、同年の1591年(天正19年)に現在の瓦町に開創したのが當山の始まりとされている。
開創当初から寺院としての機能を果たしていたのかは不明であり、推測するに当時から本願寺は天皇家との接点が色濃く、堀川六条から御所への道のりの為の休憩所(中継所)としての役割では無かったのかと思われる。


當山に安置されている本尊阿弥陀如来立像及び親鸞聖人像の軸の裏書には寛永11年(1634年)と記されており、この年が開基宗安の逝去する2年前であった事から、開創当初は寺院としての機能では無くとも、初代宗安が存命の時期から本尊(須弥壇)だけでは無く脇壇(親鸞聖人像・蓮如上人像)の設置を施された寺院としての役割を果たしていたものと思われる。以来、當山淨光寺は、令和7年度時点で創建434年となり、現在の住職(釋宗悟)は初代の釋宗安から数えて第17世となる。
また、當山の住職を世襲している北條家であるが。平時政(北條時政直江守)から数えて15世が、當山初代の釋宗安(北條宗安)とされており、現在の住職(釋宗悟)は32世となる。
當山所蔵の宝物に国宝や重文は無いが、本尊阿弥陀如来立像をはじめとする當山創建の時代からの所蔵物を、幾度にもわたる京の都の戦災から歴代の住職らが守り続けてきた。
現在の本堂は、元治元年(1864年7月)に起きた、蛤御門の変を発端とする京都御所(一条通あたり)から南の六条通あたりまでを火災で覆い尽くした≪元治の大火(どんどん焼け・鉄砲焼け)≫において焼失し、慶應2年(1866年)に再建されたものであり、現在で160年ほどの建造物となる。現在の“京町屋”と言われる建造物も、その時代の建造物であり、同じように160年ほどの歴史がある。
古文書によれば、拙寺創建の9年前の天正10年(1582年)に“本能寺の変”が拙寺から南西に約1kmの現在の堀川高校あたりで起こっているが、織田信長を討ったと言われる明智光秀を追った者から逃れるために、明智家の残人が當山に明智光秀の位牌を預けたとされているが、現在もまだ位牌は見つかってはいない。
●参考文献●
日本随筆大成<第一期>23 昭和51年:吉川弘文館 刊
諸国奇遊談 川口好和著(寛政11年 1799年)

住職挨拶
皆さま。當山のサイトにようこそお越しくださいました。淨光寺住職の釋宗悟でございます。お坊さんやお寺は、少し敷居を高く感じておられるのでしょうが、釈尊や浄土真宗の開祖親鸞はそのような考えは一切なく、衆生(一般市民)と同じ目線で法を説かれて来られました。その教えを現代にまで踏襲してこそが私たち僧侶の責務だと考え、今風で申しますと“フレンドリー”な関係でのご縁をいただいております。昨今のインバウンド観光客や物騒な世の中であります故に、門はいつも鍵をかけ閉じてはおりますが、住職の心の扉までは閉じておりませんので、どんな些細な事でも忌憚なくお尋ね下されればと思います。

| 昭和33年7月生まれ |
| 法名 釋宗悟(得度授与:昭和54年8月) |
| 淨光寺第17世住職 |
| 本願寺派特別法務員資格 |
| 震災支援京都ネット主宰 |
| 日本脱カルト協会理事 |
| 中京保護司会保護司 |
| 寺院概要 | |
|---|---|
| 寺院名 | 雒陽山淨光寺(らくようざん じょうこうじ) |
| 宗派 | 浄土真宗本願寺派(本山:西本願寺) |
| 住所 | 〒604-0827 京都市中京区高倉通二条下る瓦町560 google map |
| 電話番号 | 075-231-5061 |
| HP | https://kyoto-jokoji.com/ |
| LP | https://rakuyozan-jokoji.com |
| 交通案内 | お車の場合 京都東ICから約30分 京都南ICから約20分 ナビゲーションの電話番号検索から「075-231-5061」で検索下さい 事前にご連絡をいただけましたら、2台までは境内に駐車可能です 市営御池地下駐車場に停められると迷いますので、お避け下さい 電車の場合 地下鉄烏丸線・東西線 烏丸御池駅 1番出口より徒歩6分 阪急京都線 烏丸駅より徒歩約15分 タクシーの場合 JR京都駅八条口(新幹線口)よりタクシーで約15分 JR京都駅正面(烏丸口)よりタクシーで約10分 JR嵯峨野線二条駅よりタクシーで約10分 (運転手さんに「タカクラオシコウジアガル」)と言って下さい |
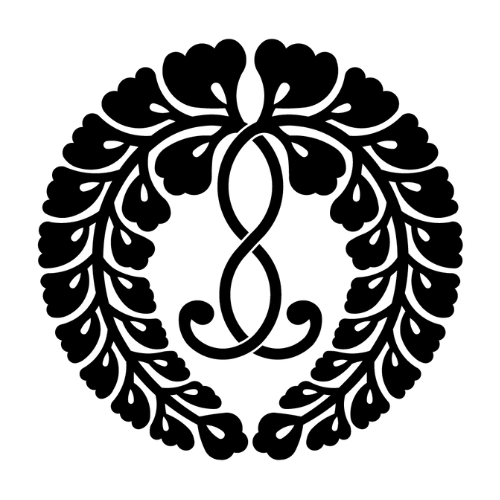
お問い合わせ
こちらのフォームにご記入の上、
「送信する」ボタンを押してください。